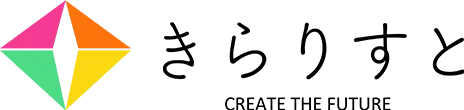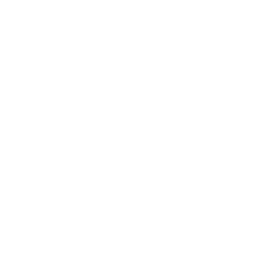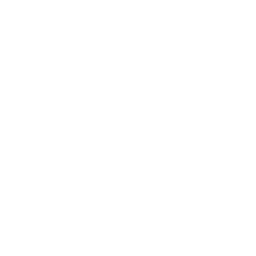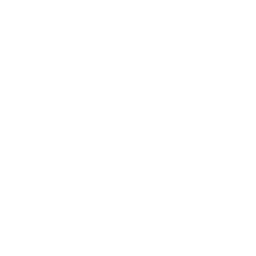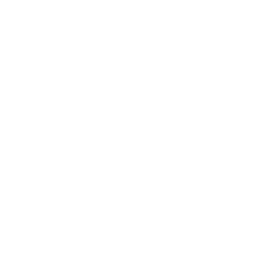【日本の地方から世界へ】地方の埋もれた地域資源を生まれ変わらせることはできるか?伝統を破壊し、創造し直すことで世界に通用する商品となる可能性

明治時代、来日した英国人建築家ジョサイア・コンドルは日本の職人技に魅了され、日本の伝統工芸における芸術性と実用性の見事な調和を高く評価しました。彼だけでなく、日本の伝統工芸の魅力に取りつかれた外国人は多くいます。しかし、かつて世界を魅了した日本の伝統工芸の多くは、後継者不足や市場の縮小という深刻な課題に直面しています。その一方、伝統に新たな息吹を吹き込み、世界市場で再評価されるという事例も生まれてきています。
この記事では、「守る」だけでなく「破壊し、創造する」ことで、伝統工芸が現代に蘇る可能性を探っていきたいと思います。
「守る」だけでは生き残れない伝統の現実
全国各地に点在する伝統工芸品は、経済産業大臣指定だけでも243品目に上る(2024年10月時点)。その生産額は最盛期(1983年)の5,410億円から2017年には927億円へと大きく減少し、最盛期の約1/5以下の水準となっています。従事者数も同様に、1979年のピーク時の28.8万人から2016年度には62,690人へと減少しています。
この衰退の背景には、生活様式の変化による需要減少、安価な海外製品との競争、後継者不足など複合的な要因がありますが、特に深刻なのは、「伝統を守る」という姿勢そのものが時に足かせとなってしまうという現実です。
多くの伝統工芸研究者が指摘するように、工芸品は元々生活用品として誕生し、その時代のライフスタイルに合わせて進化してきたものです。それが“伝統”という名のもとに形式が固定化され、現代のライフスタイルから乖離してしまったことが、衰退の一因となっているのです。
つまり、「伝統を守る」という考え方自体を見直さなければ、日本の伝統工芸は衰退の一途をたどるのみということです。
「破壊と創造」で蘇る地域の宝
伝統工芸の再生に成功している事例に共通するのは、伝統の本質を理解した上で、現代のニーズに合わせて形を変えるという、柔軟な姿勢です。
京都の老舗竹工芸メーカー「日吉屋」五代目の西堀耕太郎氏は、伝統的な和傘や提灯の技術を活かした照明デザインを開発。和紙と竹を使った伝統技法を現代的な照明デザインに融合させ、国内外の展示会で高い評価を得ています。西堀氏は著書や講演で、
「伝統と革新は対立するものではなく、伝統を深く理解することで新たな価値を生み出せる」
という考えを発信しており、その考えに私は深く賛同しています。
また、有田焼の「2016/」は、有田焼創業400年を機に発足したプロジェクトで、オランダ人デザイナーとのコラボレーションにより現代のライフスタイルに合った商品開発を推進。海外市場での評価も高まっています。
これらの成功事例に共通するのは、「伝統技術の本質」と「現代のニーズ」を橋渡しする視点です。
地域資源を「解体」し「再構築」する視点
伝統工芸の再生には、その地域資源を一度「解体」し、現代的文脈で「再構築」する視点が重要となります。
「解体」とは、伝統工芸が持つ要素を細分化して理解すること。例えば、使われている素材、製法、デザイン、用途、それぞれに宿る物語や哲学などを個別に捉え直すのです。
「伝統工芸の本質的価値は、完成品のカタチにあるのではなく、素材と技術、そこに込められた美意識にある」。これは、伝統工芸の現代化に取り組む多くのデザイナーや研究者に共通する視点です。
福井の越前和紙を例に考えてみましょう。
その特徴は、強靭さ、独特の風合い、光の透過性、持続可能な原料調達方法、1500年続く伝統技法などに分解できます。これらの要素を現代的ニーズに合わせて「再構築」することで、照明器具、建築内装材、高級パッケージング素材など、新たな商品展開が可能になったのです。実際、越前和紙の生産者と世界的なアーティストとのコラボレーションで生まれた作品は、高級ホテルに採用されるなど、新たな市場を切り開いています。
グローバル視点で考える「ジャパンブランド」
伝統工芸の再生には、国内市場だけでなく、世界市場を視野に入れた戦略が不可欠です。経済産業省が推進する「The Wonder 500」や「JAPAN BRAND 育成支援事業」など、海外での日本の伝統工芸品の評価と需要拡大が国の施策としても進められています。
経済産業省の調査によれば、海外市場で評価される日本の伝統工芸品の特徴としては、「高品質」「独自の美的感覚」「職人技」「自然素材の活用」などが挙げらるとのこと。
世界を視野に入れた活動を積極的に行っている伝統工芸もあります。
例えば、越前和紙は、「メゾン・エ・オブジェ・パリ」(イタリア・ミラノサローネ、ドイツ・フランクフルトのアンビエンテと並ぶ、ヨーロッパで最大規模のインテリア関連見本市の1つ)に出展し、国際的な評価を得ることに成功しています。この国際見本市への出展、そしてそれをきっかけに世界進出という流れは、越前和紙に限らず陶磁器や染織などの他の伝統工芸の戦略でもみられます。これらの伝統工芸品は、国際見本市に出展することで、世界中のショップオーナー、バイヤー、デザイナーに向けて日本の伝統工芸の魅力を発信しているのです。
デジタル技術が開く新たな可能性
伝統工芸の再生には、最新のデジタル技術を活用する動きも広がっています。
岐阜県高山市を含む飛騨地域の木工職人たちは、伝統的な飛騨の木工技術と最新のテクノロジーの融合に取り組んでいます。岐阜県生活技術研究所では、3Dスキャン技術を活用して木製家具をデータ化する技術を開発し、また木工用5軸CNC加工機を導入して複雑な三次元形状や曲面加工を可能にしました。
さらに、地域の職人たちは3Dモデリング技術と伝統的な組木技術を組み合わせた新しいデザインプロセスの探求を行っており、これまで困難だった複雑な木組みデザインや曲線を取り入れた家具の製作が徐々に可能になりつつあります。
これらの取り組みは、伝統工芸と先端技術の融合による新たな可能性を示す好例となっており、今後の発展が期待されています。
また、AI技術を活用した伝統模様の新デザイン開発や、VR/AR技術による工芸品のストーリー発信など、テクノロジーは伝統工芸に新たな可能性をもたらし始めています。
経済産業省の「伝統的工芸品産業支援補助金」でも、デジタル技術の活用による生産性向上や新商品開発は、重点分野となっています。デジタルとアナログの融合は、伝統工芸の新しい表現方法を生み出すだけでなく、職人の負担軽減や後継者育成にも貢献する可能性を秘めているのです。
「伝統を壊す」ことへの葛藤と挑戦
しかし、伝統を変革しようと思っても、その過程には様々な葛藤が伴うもの。
「初めは、先代から受け継いだ形を変えることに大きな抵抗がありました」。伝統工芸の新たな展開を模索する若手作家や経営者へのインタビュー記事には、こうした言葉がしばしば登場します。伝統と革新の間で生じる葛藤は、多くの伝統産業が直面する共通の課題です。
実際、多くの事例をみても、伝統を守る立場と革新を求める立場の間に必ずと言っていいほどに軋轢が生じます。しかし、双方が対話を重ねる中で新たな価値観が生まれてくるのです。葛藤と軋轢なくして、新たなものは生まれないということかもしれません。
地域資源の再生が地方創生につながる道
伝統工芸の再生は、単なる産業振興にとどまらず、地域全体の活性化につながる可能性も秘めています。
例えば、石川県小松市では、九谷焼の技術と地域資源を活かした振興策として、2016年に「九谷セラミック・ラボラトリー」を開設。若手作家の創作活動支援と観光資源としての活用を同時に進めています。
また、愛媛県今治市では、2007年から「今治タオルプロジェクト」を開始。品質基準の厳格化と統一ブランド「IMABARI TOWEL」の確立によって、それまで衰退傾向にあった地場産業を再生させることに成功しています。このプロジェクトは、地域アイデンティティの再構築と産業振興の好例となっています。
伝統工芸を核とした地域振興には、単に昔ながらの製品を作り続けるのではなく、地域の文化的価値を今日的な文脈で再解釈し、新たな価値を創造することが求められているのです。
未来へつなぐための「破壊と創造」の勇気
日本の地方に眠る豊かな伝統工芸や地域資源。それらを未来へつなぐためには、「伝統を守る」という固定観念から解放され、「伝統の本質を理解した上で創造的に再構築する」という発想の転換が必要です。
経済産業省が推進する「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」の改正においても、単なる技術や製法の保存だけでなく、現代のライフスタイルや市場ニーズに対応した新商品開発や販路開拓の重要性が強調されています。
世界が注目する「ジャパンブランド」としての可能性を最大限に引き出すためには、職人、デザイナー、経営者、行政、教育機関など、多様な立場の人々が連携し、伝統と革新の調和点を見出していく必要があります。また、海外展開する前の大前提として、まず関わる人たちが自らの伝統工芸品を日常生活で使用し、その良さを再認識することが重要です。
伝統工芸は過去の遺物ではなく、未来への創造的資源です。その本質的価値を理解し、現代的文脈で再解釈することで、日本の地方から世界へと羽ばたく新たな可能性が広がるのです。
地方の埋もれた資源を世界に通用する価値へと変革する挑戦は、各地で始まっています。近い将来、各地の取り組みが一体として繋がりをもち、大きなうねりとなって世界にインパクトを与える、そんな日が来ると信じています。
地域資源活用についてのご相談はお気軽に

「地域資源を活用してまちおこししたい」という地方行政や商工会議所のご担当者様、また、地域産業に関わる事業者様や職人様、お困りのことがあればご相談ください。